つばめろま〜なから、なにかを知りたい貴方へ。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
「水平線のぼくら 天使のジャンパー」仁木英之(角川春樹事務所)
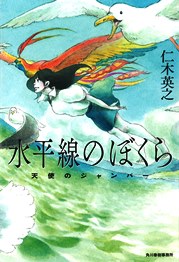
「撲撲少年」が、仁木さんの青春スポーツ小説・第1段とすれば、これが第2段という位置づけになりましょうか。前作が総合格闘技、本作がノルディックスキーと、すごくマイナーではないけれどメジャーとはいえないところをついてきて、競技への興味もわく分、物語がより興味深く読めるようになります。川西蘭の自転車小説とも似た感じを持ちました。
舞台の奄美が、種子島と沖縄本島の中間にあるということもはじめて認識したくらいな私、その風土や社会や問題、そこに生まれ育ち暮らすことの想いを底にして、その地に違和感のある競技を持ってきた作品には、強く惹かれるものがありました。沖縄どころか近くの海から見える伊豆大島にすら行ったことがないので、離島への憧れもあり胸が騒ぐのです。
ストーリーも熱血あり恋情あり不思議さありで面白く読み進めました。都会の高校生たちの話だと、こんなに純粋にはならないでしょうから、ここでも舞台設定が生きています。最後の方になって、ヒロインの存在がどういうものなのか、書ききれていない感じでよく理解できない部分もありましたが、ツンデレ系美少女の魅力は大きいものでした。心に残る1冊という感じです。

にほんブログ村
「撲撲少年」が、仁木さんの青春スポーツ小説・第1段とすれば、これが第2段という位置づけになりましょうか。前作が総合格闘技、本作がノルディックスキーと、すごくマイナーではないけれどメジャーとはいえないところをついてきて、競技への興味もわく分、物語がより興味深く読めるようになります。川西蘭の自転車小説とも似た感じを持ちました。
舞台の奄美が、種子島と沖縄本島の中間にあるということもはじめて認識したくらいな私、その風土や社会や問題、そこに生まれ育ち暮らすことの想いを底にして、その地に違和感のある競技を持ってきた作品には、強く惹かれるものがありました。沖縄どころか近くの海から見える伊豆大島にすら行ったことがないので、離島への憧れもあり胸が騒ぐのです。
ストーリーも熱血あり恋情あり不思議さありで面白く読み進めました。都会の高校生たちの話だと、こんなに純粋にはならないでしょうから、ここでも舞台設定が生きています。最後の方になって、ヒロインの存在がどういうものなのか、書ききれていない感じでよく理解できない部分もありましたが、ツンデレ系美少女の魅力は大きいものでした。心に残る1冊という感じです。
にほんブログ村
PR
「盤上に散る」塩田武士(講談社)
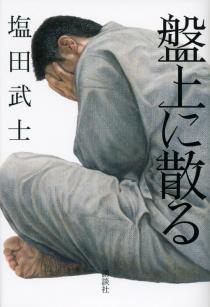
プロ棋士を描いた「盤上のアルファ」から登場人物などが繋がる、将棋の真剣師にまつわる話。なので併せて読んだ方がよくわかるのですが、プロ棋士の厳しい勝負の世界を描いた前作と、何人もの生き様がミステリアスに明かされていく本作ではちょっとジャンルが違い、読感も異なります。私はどちらもすごく楽しんで読めたので問題ありませんでしたが。
作者の本で初めて読んだ「女神のタクト」のヒロインほどではありませんが、本作の主人公もアラフォー独身の姉御肌で酒が入ると暴力的になるなど、イメージ的に共通点がありました。そんなタイプが好きなわけではありませんが、キャラが強いのは物語にとっては魅力です。冒頭、母を亡くしたばかりの彼女からは思いもよらない感じでしたが、進むほどにどんどん生き生きとしていきました。
相棒のチンピラ君も、人の良さや意外と小心者のところが愛すべき人物。その他、次々と個性の強い人たちが登場し良い具合に絡み合って、知りたい真相へと近づいていく構成が良くできていて満足度の高い作品となっています。ついでに、関西が舞台だから良いのかも、これが東京の話だったらもっと息苦しいものになってしまいそうに思います。
真剣師という賭博将棋の世界に立ち入りすぎず、駒づくり職人のこととか、将棋が身近にある人たちとか、将棋文化への愛に満ちているのも、コテコテなのにさわやかな印象を与えてくれます。ソフトやネットでいつでも対戦できる世の中ですが、コンピューターの中の1ゲームにしてしまってはいけないのですね。
さて、最近の小説を読んでいてよく思うことですが、私と同年代の人物が登場してきたとき、色褪せたモノクロ写真のような昔の時代を生きてきた人として描かれるのに、軽いショックを受けます。本作ではヤクザな刑事がそうです。確かに自分の子供の頃を考えれば、ここまで貧乏ではなかったにしろ、街も人も自然も今のように小綺麗ではなかったと思い出しますが、生命力にはあふれていたかもしれません。
今ここで何故か出合った、いくつもの世代の人物の過去が交錯していくのも、一つの深い魅力になっています。

にほんブログ村
プロ棋士を描いた「盤上のアルファ」から登場人物などが繋がる、将棋の真剣師にまつわる話。なので併せて読んだ方がよくわかるのですが、プロ棋士の厳しい勝負の世界を描いた前作と、何人もの生き様がミステリアスに明かされていく本作ではちょっとジャンルが違い、読感も異なります。私はどちらもすごく楽しんで読めたので問題ありませんでしたが。
作者の本で初めて読んだ「女神のタクト」のヒロインほどではありませんが、本作の主人公もアラフォー独身の姉御肌で酒が入ると暴力的になるなど、イメージ的に共通点がありました。そんなタイプが好きなわけではありませんが、キャラが強いのは物語にとっては魅力です。冒頭、母を亡くしたばかりの彼女からは思いもよらない感じでしたが、進むほどにどんどん生き生きとしていきました。
相棒のチンピラ君も、人の良さや意外と小心者のところが愛すべき人物。その他、次々と個性の強い人たちが登場し良い具合に絡み合って、知りたい真相へと近づいていく構成が良くできていて満足度の高い作品となっています。ついでに、関西が舞台だから良いのかも、これが東京の話だったらもっと息苦しいものになってしまいそうに思います。
真剣師という賭博将棋の世界に立ち入りすぎず、駒づくり職人のこととか、将棋が身近にある人たちとか、将棋文化への愛に満ちているのも、コテコテなのにさわやかな印象を与えてくれます。ソフトやネットでいつでも対戦できる世の中ですが、コンピューターの中の1ゲームにしてしまってはいけないのですね。
さて、最近の小説を読んでいてよく思うことですが、私と同年代の人物が登場してきたとき、色褪せたモノクロ写真のような昔の時代を生きてきた人として描かれるのに、軽いショックを受けます。本作ではヤクザな刑事がそうです。確かに自分の子供の頃を考えれば、ここまで貧乏ではなかったにしろ、街も人も自然も今のように小綺麗ではなかったと思い出しますが、生命力にはあふれていたかもしれません。
今ここで何故か出合った、いくつもの世代の人物の過去が交錯していくのも、一つの深い魅力になっています。
にほんブログ村
DUO MORITA in TOKYO
2014年7月26日 スタジオSK(新高円寺)
ドイツに住み活動されている森田ご夫妻、森田満留さん(チェロ)&森田竜一さん(ピアノ)の「デュオ・モリタ」による来日公演。私の妹がドイツ居留中にお世話になったということで、ドイツの音がするからぜひ聴いてみてと誘われ、フォーレとピアソラとショパンの曲目にも惹かれ、行ってきました。
50席もない小さい会場、でも天井は高く夏の夕刻なので天窓から明るい外光も入り、アットホームなサロンコンサートという雰囲気の中ではじまったコンサート。1曲目から、実に刺激的でした。切れのあるチェロ、華やかなピアノ、ふたつの音が魅惑的に絡み合い、クラシックのデュオとは思えないほどに激しくて、ロマンチックな演奏です。
フォーレの2曲目と3曲目はピアノの独奏、そしてチェロが再登場してデュオとなり奏でられたピアソラは、ものすごくカッコイイのでした。リベル・タンゴは有名な曲ですが、これほどステキな演奏ははじめてでした。
休憩が入り、後半はショパン。ショパンがチェロの曲を書いていたということもはじめて知りましたが、ピアノ協奏曲を書いているのですから不思議ではありません。チェロの音色を美しく響かせながら、やはりショパンだなぁと思わせる曲でした。心地よく、どこかもの悲しく。
アンコールの2曲めに、先ほど弾いたピアソラのミケランジェロ70をやって、満ち足りた気持ちの中で終了です。良い余韻でした。帰りにCDを1枚買ったのは、買わずにいられない気持ちでのことです。
前週に山下洋輔ビッグバンドを聴いたばかりでのデュオでしたが、印象的に決して負けないほど、エネルギーをいっぱいもらえるコンサートでありました。
◆プログラム
◯フォーレ/チェロとピアノのためのソナタ第1番 作品109
パヴァーヌ
ノクターン第6番 作品63
◯ピアソラ/リベル・タンゴ
ミロンガニ短調
ミケランジェロ70
◯ショパン/ピアノとチェロのためのソナタ 作品65

にほんブログ村
2014年7月26日 スタジオSK(新高円寺)
ドイツに住み活動されている森田ご夫妻、森田満留さん(チェロ)&森田竜一さん(ピアノ)の「デュオ・モリタ」による来日公演。私の妹がドイツ居留中にお世話になったということで、ドイツの音がするからぜひ聴いてみてと誘われ、フォーレとピアソラとショパンの曲目にも惹かれ、行ってきました。
50席もない小さい会場、でも天井は高く夏の夕刻なので天窓から明るい外光も入り、アットホームなサロンコンサートという雰囲気の中ではじまったコンサート。1曲目から、実に刺激的でした。切れのあるチェロ、華やかなピアノ、ふたつの音が魅惑的に絡み合い、クラシックのデュオとは思えないほどに激しくて、ロマンチックな演奏です。
フォーレの2曲目と3曲目はピアノの独奏、そしてチェロが再登場してデュオとなり奏でられたピアソラは、ものすごくカッコイイのでした。リベル・タンゴは有名な曲ですが、これほどステキな演奏ははじめてでした。
休憩が入り、後半はショパン。ショパンがチェロの曲を書いていたということもはじめて知りましたが、ピアノ協奏曲を書いているのですから不思議ではありません。チェロの音色を美しく響かせながら、やはりショパンだなぁと思わせる曲でした。心地よく、どこかもの悲しく。
アンコールの2曲めに、先ほど弾いたピアソラのミケランジェロ70をやって、満ち足りた気持ちの中で終了です。良い余韻でした。帰りにCDを1枚買ったのは、買わずにいられない気持ちでのことです。
前週に山下洋輔ビッグバンドを聴いたばかりでのデュオでしたが、印象的に決して負けないほど、エネルギーをいっぱいもらえるコンサートでありました。
◆プログラム
◯フォーレ/チェロとピアノのためのソナタ第1番 作品109
パヴァーヌ
ノクターン第6番 作品63
◯ピアソラ/リベル・タンゴ
ミロンガニ短調
ミケランジェロ70
◯ショパン/ピアノとチェロのためのソナタ 作品65
にほんブログ村
最初のものから少し時間が経ってしまいましたが、この3ヶ月の間に聴きに行ったまったく違うジャンル(笑)の3つのコンサート、「谷山浩子&ROLLYのからくり人形楽団」と「近藤岳オルガンリサイタル」、「山下洋輔スペシャルビッグバンド」で思ったことを記します。
◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆
谷山浩子とROLLYによる異色のコラボレーション、一昨年に登場したときには驚きましたが、しっかりと形になってきた感があります。この日はANNEXと銘打ったように一部メンバーは違いますが、その場限りのものではなく、バンドとしての在り方が見えていたように思えました。ソロシンガーとして40年やってきた浩子さんにとって、初めてのバンド活動といえるかもしれない、と。
たとえば浩子さんとAQ、斉藤ネコでも、息のあったバンドのような形態ではありますが、ネコさんがどんなにハチャメチャにバイオリンを弾きまくっても、基本は谷山ワールドの構築と拡張です。オーケストラ編成の猫森楽団も同様。
けれど、ROLLYさんは谷山ワールドに敬意を表しながらも、その一部を侵略して自分のものにしてしまおうという野心を覗かせます。ROLLYという特異なキャラクターだからこそ可能な仕業。それに浩子さんも対抗して、新しい自分を構築し直して見せてくれる感じ。二人が楽しくハーモナイズしながらせめぎあう、二人とも良い歳になったからこそ、かもしれません。
昨春に観た「からくり人形楽団」ファーストライブよりもずっとそれを感じたのは、成熟したこともあるでしょう、それと山口トモという奇妙なドラマーが加わっていたこと、そして円形劇場だったことも大きな要因だったと思います。ジャズの即興のように音楽が新しく生まれていく現場に居合わせた臨場感の興奮と歓びを、ものすごく強く感じました。
青山円形劇場という大好きな場がなくなってしまうのは、とても残念なことです。音楽だけでなく演劇も観ました。ブリキの自発団の演出には興奮したものですし、新感線も近くて迫力でした。通常のステージとは全く違う演出を強いられ、創造力、対応力が試される劇場だと思います。
音楽の場合は演奏者同士が向き合うと同時に、その先にお客さんの顔が見えるという、客側からは後ろ向きの演奏者の向こうに前向きの演奏者の顔があり、その先にやはりお客さんの顔が見える、つまりは見ている自分も見られる存在となる、不思議な空間。
ここでたぶん20回ほども浩子さんのライブを見てきたでしょうか、彼女に最もふさわしい会場であったことは、この日あらためて確認できたところです。すり鉢状の一番低いステージを円形に囲んだ400足らずの席が、谷山浩子の世界観、共演者との関係、お客さんとの関係をとびきり優しいものにしておりました。これは大きなホールや、スペースゼロでも難しいのです。
行政も企業も、文化に金を出せなくなってきた今、老朽化という名目で拠点そのものがどんどん失われていきそうです。ある程度は仕方ないけれど、オリンピックなんかに巨費を掛けられるなら、もっと本当に大切なものがなにか、見つめて欲しいものです。
谷山さんなど、金(ヒット)は生まないけれど質(アート性)の高い、精神文化の象徴のような存在であると思います。その精神に親密にふれることができる新たな場が誕生してほしいものです。
◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆
妻がオルガンを習っている近藤先生、以前にもコンサートを聴いたことがありますが、今回は曲も面白いからということで、楽しみにしておりました…のは、昨年10月のこと。ホールの前で開場を待っていると、出演者急病のため中止になっていたのです。
それから7ヶ月後のリベンジ、先生ものすごく気合いが入っていると聞いて、さらに楽しみにして、前回は踏み入れることのできなかったミューザ川崎の客席へと、初めて行くことができたのでした。それにしても、これまでにいくつものパイプオルガンを見てきましたが、いつも巨大で美しい存在感に圧倒されてしまいます。それも、表に見えているパイプは一部だけで、裏に何千本も隠れているのですから。
ホールは違いますがうちの妻も発表会の時に、あんな巨大な楽器をあんな高い所で弾いているのかと思うと、感心もし、羨ましくもあり。一度弾いたら病みつきになるでしょうねぇ。
オルガン曲というと、どうしてもバッハ中心の中世宗教音楽になりますが、今回の作品は1930年に書かれた2つの曲と、それに触発されて書かれた近藤先生の作品ということで興味深く、そして素晴らしい演奏を聴くことができました。
L.ヴィエルヌ作「オルガン交響曲第6番」は荘厳な大曲。
近藤岳作「オルガンと2本のトランペットのための『来たれ、創り主なる聖霊』」はトランペット2本も加わって爽やかさも感じる曲。
M.デュリュフレ作「前奏曲、アダージョと『来たれ、創り主なる聖霊』によるコラール変奏曲はより現代風な感じのある曲。
家に練習用のオルガンがあるので、私もたまに即興で弾いたりするのですが、音色はいろいろ変えられても、鍵盤のタッチで音の変化を付けることができないので、表現が難しい楽器だと思います。
それが、オルガンそのものの違いは置いといて、一流の音楽家が演奏すればこんなにも自由に表情豊かに弾けるものかと、感動を覚えたのでした。
終演後、楽屋にも訪問させてもらいましたが、シンフォニーホールの楽屋ってこんなに広いんだと驚きながら、難曲の演奏を成功させた清々しい充実感を漂わせる近藤先生にご挨拶したところで、コンサートは終了となりました。
◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆
山下洋輔 (Piano)金子 健 (Bass)、高橋信之介 (Drums)
[Trumpet]エリック宮城、佐々木史郎、木幡光邦、高瀬龍一
[Trombone]松本 治(Conduct)、中川英二郎、片岡雄三、山城純子
[Saxophone]池田 篤、米田裕也、川嶋哲郎、竹野昌邦、小池 修
巨匠・山下さんも70歳を超え、いま聴いておかないと突然に…などと考えてしまったのは、氏のエッセイ「猫返し神社」で、次の猫を飼いたいけれど先に逝くかもしれないからもう…というようなことが書かれていたからでした。そんなタイミングでこのコンサートの開催を知ったので、平日にも拘わらずチケットを取ってしまった次第。
そうした年齢的な懸念はまったく感じさせない、20年前よりは少しパワーダウンしているかもしれませんが、熱くて激しい、華やかでダンディな、さらに円熟味も増した演奏を聴かせてくれました。
曲目はムソルグスキー「展覧会の絵」とドヴォルザーク「新世界より」、場所もクラシック中心に使われるオーチャードホールと、期待感も大きく膨らみます。どちらも、私の期待感などはるかに上回る、素晴らしい演奏でした。
「展覧会の絵」は組曲ですので、短い1曲ごとに表情が変わっていき、独奏者の個性も際だつところは、まさにジャズ向きと言えましょう。原曲を現代風に解釈し、時に猥雑に、時にセクシーに、でも全体として品位も保ちながらの大胆なアレンジで、とても楽しく聴かせてもらいました。
「新世界より」は、ドヴォルザークの交響曲第9番を、そのまま全4楽章で聴かせるもの。もちろん、原曲の主題をどこまでもジャズの魅力たっぷりにしたアレンジですが、洗練されていて、遊び心もあふれていて、音楽としての驚きと心地よさに満ちていて、まさしくシンフォニーならではの醍醐味を楽しませてくれました。
アンコールはジャズらしくソロを繋いだりして盛り上がり、終了です。
演奏の見事さは、山下さんのピアノによる盛り上げ、編曲し指揮しながらトロンボーンも吹く松本さんへの信頼感、個々のプレイヤーの高い感性と技術、すべてが相乗したものであったと思います。私にとっては馴染みのない出演者も多かったのですが、皆さん、世界の山下洋輔が集めただけの熟達した逸材揃いでありました。
テレビでは見たことのあるエリック宮城のトランペットは画面の中より何倍も刺激的でしたし、川嶋哲郎の吹くフルートも新鮮に響いたし、高橋信之介のドラムも全体を支える安定感が素晴らしかったし…と、枚挙に暇がありません。
全体を通して言えば、クラシックの名曲をジャズ風にアレンジしてみました、というようなものとはまったく次元の異なる、敬意を表しながらの挑戦であり、新しい世界の創造であったと、胸に刻んでおります。

にほんブログ村
◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆
「からくり人形楽団ANNEX」
2014.5.10(青山円形劇場)谷山浩子とROLLYによる異色のコラボレーション、一昨年に登場したときには驚きましたが、しっかりと形になってきた感があります。この日はANNEXと銘打ったように一部メンバーは違いますが、その場限りのものではなく、バンドとしての在り方が見えていたように思えました。ソロシンガーとして40年やってきた浩子さんにとって、初めてのバンド活動といえるかもしれない、と。
たとえば浩子さんとAQ、斉藤ネコでも、息のあったバンドのような形態ではありますが、ネコさんがどんなにハチャメチャにバイオリンを弾きまくっても、基本は谷山ワールドの構築と拡張です。オーケストラ編成の猫森楽団も同様。
けれど、ROLLYさんは谷山ワールドに敬意を表しながらも、その一部を侵略して自分のものにしてしまおうという野心を覗かせます。ROLLYという特異なキャラクターだからこそ可能な仕業。それに浩子さんも対抗して、新しい自分を構築し直して見せてくれる感じ。二人が楽しくハーモナイズしながらせめぎあう、二人とも良い歳になったからこそ、かもしれません。
昨春に観た「からくり人形楽団」ファーストライブよりもずっとそれを感じたのは、成熟したこともあるでしょう、それと山口トモという奇妙なドラマーが加わっていたこと、そして円形劇場だったことも大きな要因だったと思います。ジャズの即興のように音楽が新しく生まれていく現場に居合わせた臨場感の興奮と歓びを、ものすごく強く感じました。
青山円形劇場という大好きな場がなくなってしまうのは、とても残念なことです。音楽だけでなく演劇も観ました。ブリキの自発団の演出には興奮したものですし、新感線も近くて迫力でした。通常のステージとは全く違う演出を強いられ、創造力、対応力が試される劇場だと思います。
音楽の場合は演奏者同士が向き合うと同時に、その先にお客さんの顔が見えるという、客側からは後ろ向きの演奏者の向こうに前向きの演奏者の顔があり、その先にやはりお客さんの顔が見える、つまりは見ている自分も見られる存在となる、不思議な空間。
ここでたぶん20回ほども浩子さんのライブを見てきたでしょうか、彼女に最もふさわしい会場であったことは、この日あらためて確認できたところです。すり鉢状の一番低いステージを円形に囲んだ400足らずの席が、谷山浩子の世界観、共演者との関係、お客さんとの関係をとびきり優しいものにしておりました。これは大きなホールや、スペースゼロでも難しいのです。
行政も企業も、文化に金を出せなくなってきた今、老朽化という名目で拠点そのものがどんどん失われていきそうです。ある程度は仕方ないけれど、オリンピックなんかに巨費を掛けられるなら、もっと本当に大切なものがなにか、見つめて欲しいものです。
谷山さんなど、金(ヒット)は生まないけれど質(アート性)の高い、精神文化の象徴のような存在であると思います。その精神に親密にふれることができる新たな場が誕生してほしいものです。
◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆
「近藤岳オルガンリサイタル」
2014年6月1日(ミューザ川崎)妻がオルガンを習っている近藤先生、以前にもコンサートを聴いたことがありますが、今回は曲も面白いからということで、楽しみにしておりました…のは、昨年10月のこと。ホールの前で開場を待っていると、出演者急病のため中止になっていたのです。
それから7ヶ月後のリベンジ、先生ものすごく気合いが入っていると聞いて、さらに楽しみにして、前回は踏み入れることのできなかったミューザ川崎の客席へと、初めて行くことができたのでした。それにしても、これまでにいくつものパイプオルガンを見てきましたが、いつも巨大で美しい存在感に圧倒されてしまいます。それも、表に見えているパイプは一部だけで、裏に何千本も隠れているのですから。
ホールは違いますがうちの妻も発表会の時に、あんな巨大な楽器をあんな高い所で弾いているのかと思うと、感心もし、羨ましくもあり。一度弾いたら病みつきになるでしょうねぇ。
オルガン曲というと、どうしてもバッハ中心の中世宗教音楽になりますが、今回の作品は1930年に書かれた2つの曲と、それに触発されて書かれた近藤先生の作品ということで興味深く、そして素晴らしい演奏を聴くことができました。
L.ヴィエルヌ作「オルガン交響曲第6番」は荘厳な大曲。
近藤岳作「オルガンと2本のトランペットのための『来たれ、創り主なる聖霊』」はトランペット2本も加わって爽やかさも感じる曲。
M.デュリュフレ作「前奏曲、アダージョと『来たれ、創り主なる聖霊』によるコラール変奏曲はより現代風な感じのある曲。
家に練習用のオルガンがあるので、私もたまに即興で弾いたりするのですが、音色はいろいろ変えられても、鍵盤のタッチで音の変化を付けることができないので、表現が難しい楽器だと思います。
それが、オルガンそのものの違いは置いといて、一流の音楽家が演奏すればこんなにも自由に表情豊かに弾けるものかと、感動を覚えたのでした。
終演後、楽屋にも訪問させてもらいましたが、シンフォニーホールの楽屋ってこんなに広いんだと驚きながら、難曲の演奏を成功させた清々しい充実感を漂わせる近藤先生にご挨拶したところで、コンサートは終了となりました。
◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆ ◆ ☆
「山下洋輔 スペシャルビッグバンド」
2014年7月17日(オーチャードホール)山下洋輔 (Piano)金子 健 (Bass)、高橋信之介 (Drums)
[Trumpet]エリック宮城、佐々木史郎、木幡光邦、高瀬龍一
[Trombone]松本 治(Conduct)、中川英二郎、片岡雄三、山城純子
[Saxophone]池田 篤、米田裕也、川嶋哲郎、竹野昌邦、小池 修
巨匠・山下さんも70歳を超え、いま聴いておかないと突然に…などと考えてしまったのは、氏のエッセイ「猫返し神社」で、次の猫を飼いたいけれど先に逝くかもしれないからもう…というようなことが書かれていたからでした。そんなタイミングでこのコンサートの開催を知ったので、平日にも拘わらずチケットを取ってしまった次第。
そうした年齢的な懸念はまったく感じさせない、20年前よりは少しパワーダウンしているかもしれませんが、熱くて激しい、華やかでダンディな、さらに円熟味も増した演奏を聴かせてくれました。
曲目はムソルグスキー「展覧会の絵」とドヴォルザーク「新世界より」、場所もクラシック中心に使われるオーチャードホールと、期待感も大きく膨らみます。どちらも、私の期待感などはるかに上回る、素晴らしい演奏でした。
「展覧会の絵」は組曲ですので、短い1曲ごとに表情が変わっていき、独奏者の個性も際だつところは、まさにジャズ向きと言えましょう。原曲を現代風に解釈し、時に猥雑に、時にセクシーに、でも全体として品位も保ちながらの大胆なアレンジで、とても楽しく聴かせてもらいました。
「新世界より」は、ドヴォルザークの交響曲第9番を、そのまま全4楽章で聴かせるもの。もちろん、原曲の主題をどこまでもジャズの魅力たっぷりにしたアレンジですが、洗練されていて、遊び心もあふれていて、音楽としての驚きと心地よさに満ちていて、まさしくシンフォニーならではの醍醐味を楽しませてくれました。
アンコールはジャズらしくソロを繋いだりして盛り上がり、終了です。
演奏の見事さは、山下さんのピアノによる盛り上げ、編曲し指揮しながらトロンボーンも吹く松本さんへの信頼感、個々のプレイヤーの高い感性と技術、すべてが相乗したものであったと思います。私にとっては馴染みのない出演者も多かったのですが、皆さん、世界の山下洋輔が集めただけの熟達した逸材揃いでありました。
テレビでは見たことのあるエリック宮城のトランペットは画面の中より何倍も刺激的でしたし、川嶋哲郎の吹くフルートも新鮮に響いたし、高橋信之介のドラムも全体を支える安定感が素晴らしかったし…と、枚挙に暇がありません。
全体を通して言えば、クラシックの名曲をジャズ風にアレンジしてみました、というようなものとはまったく次元の異なる、敬意を表しながらの挑戦であり、新しい世界の創造であったと、胸に刻んでおります。
にほんブログ村
「聖夜」佐藤多佳子(文春文庫)

第二音楽室シリーズの2冊目、前巻は中短編4作でしたが、こちらは1冊1作の読み応えある作品でした。高校のオルガン部が舞台、主人公も男子となって、同じシリーズには思えない感じでしたが、音楽を中心にさまざまな人間関係が描かれるのは同様です。
牧師の子、キリスト教の学校、礼拝堂、パイプオルガン。この年頃がいちばん、自分自身について知ろうとする中で信仰というようなことにも思いを巡らせると思われます、主人公のような家庭環境ならばさらなる葛藤が大きいのも当然でしょう。高校三年生のクリスマスということで、数ヶ月後には大学生となってまずはひとつ大人の世界に入る主人公の成長物語として、とても納得のいく作品になっていました。
家人が習っているので我が家には電子オルガンがあり弾くことができますし、パイプオルガンのコンサートも何度か聴いたことがありますので(作中舞台モデルの青学礼拝堂でも聞きました)、この特殊な楽器についてはある程度の知識はありますが、それでもいろいろと発見させられました。作者もオルガニストに聞きながらでしょうが、音楽描写の的確さもさすがと思います。
本作が男子を主人公にしたことで、女性作家ではありますが男子目線で見た女の子たちがかわいく魅力的でした。といっても、ラノベ的なアイコン化にはならず、天野も青木も意志の強い人間性が感じられるのがとても良かった。
ところで、このシリーズには作中の年が記されていて、本作の主人公はちょうど私と同じ歳ということなのでした。たしかに、あの頃の匂いが満ちています。こずかいを持ってレコード屋に行って新しい音楽と出会う喜び。鞄に入れて簡単に持って帰れるCDとはちょっと違う感覚です。FM放送をカセットテープに録音しては繰り返し聴いていた、あの頃。
まだ、大がかりなイルミネーションなどなくて、ツリーだけが電球を巻かれ静かに光を点滅させていた、神聖なクリスマスの風景。そう、あの頃の夜は街中でも今よりずっと暗くて、盛り場だってもっと猥雑で、私たちにとっての世界の在り様は不可解きわまりなかったと思います。
そんな気分を思い出させてくれたのも嬉しいですが、きっと今の子の心にも深く刻まれる作品であると思います。

にほんブログ村
第二音楽室シリーズの2冊目、前巻は中短編4作でしたが、こちらは1冊1作の読み応えある作品でした。高校のオルガン部が舞台、主人公も男子となって、同じシリーズには思えない感じでしたが、音楽を中心にさまざまな人間関係が描かれるのは同様です。
牧師の子、キリスト教の学校、礼拝堂、パイプオルガン。この年頃がいちばん、自分自身について知ろうとする中で信仰というようなことにも思いを巡らせると思われます、主人公のような家庭環境ならばさらなる葛藤が大きいのも当然でしょう。高校三年生のクリスマスということで、数ヶ月後には大学生となってまずはひとつ大人の世界に入る主人公の成長物語として、とても納得のいく作品になっていました。
家人が習っているので我が家には電子オルガンがあり弾くことができますし、パイプオルガンのコンサートも何度か聴いたことがありますので(作中舞台モデルの青学礼拝堂でも聞きました)、この特殊な楽器についてはある程度の知識はありますが、それでもいろいろと発見させられました。作者もオルガニストに聞きながらでしょうが、音楽描写の的確さもさすがと思います。
本作が男子を主人公にしたことで、女性作家ではありますが男子目線で見た女の子たちがかわいく魅力的でした。といっても、ラノベ的なアイコン化にはならず、天野も青木も意志の強い人間性が感じられるのがとても良かった。
ところで、このシリーズには作中の年が記されていて、本作の主人公はちょうど私と同じ歳ということなのでした。たしかに、あの頃の匂いが満ちています。こずかいを持ってレコード屋に行って新しい音楽と出会う喜び。鞄に入れて簡単に持って帰れるCDとはちょっと違う感覚です。FM放送をカセットテープに録音しては繰り返し聴いていた、あの頃。
まだ、大がかりなイルミネーションなどなくて、ツリーだけが電球を巻かれ静かに光を点滅させていた、神聖なクリスマスの風景。そう、あの頃の夜は街中でも今よりずっと暗くて、盛り場だってもっと猥雑で、私たちにとっての世界の在り様は不可解きわまりなかったと思います。
そんな気分を思い出させてくれたのも嬉しいですが、きっと今の子の心にも深く刻まれる作品であると思います。
にほんブログ村
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新CM
[06/01 WaxJelia]
[01/25 本が好き!運営担当]
[03/27 うらたじゅん]
[10/28 のりこ]
[08/04 つばめろま〜な]
最新記事
(01/21)
(12/30)
(01/02)
(02/06)
(01/01)
最新TB
プロフィール
HN:
つばめろま〜な
性別:
男性
趣味:
絵・音・文・歩
自己紹介:
長年、同人誌で創作漫画を発表してきましたが、本当は小説が主な表現手段。職業はコピーライターで、趣味は楽器を鳴らすことなど。
下記に作品等アップ中です。よろしくお願いします!
■マンガ作品 COMEE
http://www.comee.jp/userinfo.php?userid=1142
■イラスト作品 pixiv
https://www.pixiv.net/users/31011494
■音楽作品 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UChawsZUdPAQh-g4WeYvkhcA
■近況感想雑記 Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005202256040
下記に作品等アップ中です。よろしくお願いします!
■マンガ作品 COMEE
http://www.comee.jp/userinfo.php?userid=1142
■イラスト作品 pixiv
https://www.pixiv.net/users/31011494
■音楽作品 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UChawsZUdPAQh-g4WeYvkhcA
■近況感想雑記 Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005202256040
ブログ内検索
最古記事
(09/30)
(10/06)
(10/10)
(10/12)
(10/12)
P R
忍者アナライズ
忍者アナライズ
忍者アナライズ
忍者アナライズ

