つばめろま〜なから、なにかを知りたい貴方へ。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
そんなわけで、私の住んでいる鎌倉市の大船エリアの桜を紹介します。
露天が出るので飲み食いもできる、三菱の企業バンドや隣の女子大などのブラバン演奏もある、最後には三菱商品の当たる抽選会もあります。昨年は震災直後で中止だったと思いますので、近くの人は待ち望んでいたイベントだったでしょう、多くの人で賑わっていました。こうした地元との結びつきを大切にする企業姿勢は良いものだと思います。三菱グループっぽい気もします。
西口では、谷戸池を囲む桜が美しいのですが、今年は訪れるタイミングが取れそうになく、写真を掲載できません。ライトアップもするようなので、夜桜を見たいと思うのですが、深夜帰宅になってしまう私は未だ見る機会に恵まれておりません。
中でも久成寺の桜は見事。門外の大樹が出迎え、境内の桜は庭園風景を美しく彩っています。
鎌倉市内に行けば、もっとダイナミックな桜を楽しめるのですが、今年は開花が遅く、満開時期が鎌倉まつりと重なってしまいましたので、人出が多すぎて行く気になれません。花が来週まで持てば、鎌倉山にいきたいところですが、先日のような春の嵐が来ないことを祈る所です。なお、鎌倉の桜花は、東京に比べると2〜3日ほど遅いように思います。
PR
「魔神航路」仁木英之(PHP文芸文庫)
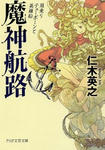
本当に精力的に次々と作品を生み出している作者の、また新しいストーリーの始まりです。文庫本の書き下ろしということで、1巻完結かと思って読み始めたのですが、ギリシア神話の世界を舞台にした話がそんなに簡単に終わるわけはありませんでした。
それにしても、中国の神仙、天竺までの仏僧行脚、日本の八百万神、江戸初期の切支丹ときて、ついにギリシアの神々と、宗教観を取り入れることで小説としての深みが増していきます。世の中には単に設定として使う作品も多いですが、しっかり考証されているので知的好奇心をも刺激してくれるのが素晴らしいです。
さて、中国でも日本でもなく、古代(神代)とはいえ西欧での物語、しかして中身は現代日本の若者たちの青春群像なのですが、ギリシア神話の名だたる神や英雄たちが続々と登場して活躍する展開が新鮮で楽しいものでした。
もちろん、その筆頭は魔神・テューポーンで、そのかわいらしさにすっかり魅せられてしまいます(本来は荒ぶる男神のはずなのですが、神に性別はないと本人も言っております)。アニメなどでよくある萌えキャラタイプであると言えばそうで、当然に作者もそこを狙ってキャラを立てていると思われますが、しかしそれだけでは終わらない、神としての奥深さが描かれているところが魅力です。
それは、神の時間と人の時間の違いなのかもしれません。神と人が融合するというこの話の肝は、そこにあるかと思います。古代と現代の時の壁を超える経験をした神や人たちが、そのうち出るだろう2巻ではもっとダイナミックに動き回るかと思うと、続きが楽しみです。
それにしても、ギリシア神話は小学生の頃に児童書で読んだ記憶があるくらいですが、とんでもない神様たちの話です。こんな話が何千年も前に生まれていたというのが驚きです。中国4千年の歴史もすごいですが、そこにキリストやブッダや孔子が生まれた文化的ベースがあるわけです。
それに比べて日本の神話なんてちっぽけなものだよなぁと思ったり。別に小さいことは悪くないのですが。日本が神国だなんて勘違いするたびに大きな過ちを冒してきたわけで、日本文化の素晴らしい神髄はもっと別のところにあるのだと理解していなければなりません。と、いつも仁木氏の作品には気付かされるのです。
テューポーン以外にも、幼なじみの女の子や双子の女の子、介抱してくれたギリシアの少女もまた登場してほしいしと、なかなかステキな女性も多く、どんな展開を描いてくれるか。もちろん、男どもの熱いバトルアクションや冒険も見所ですが。主人公の性格がちょっと・・というところも、変に感情移入し過ぎないので良いのかも知れません。続巻を待望することにしましょう。
本当に精力的に次々と作品を生み出している作者の、また新しいストーリーの始まりです。文庫本の書き下ろしということで、1巻完結かと思って読み始めたのですが、ギリシア神話の世界を舞台にした話がそんなに簡単に終わるわけはありませんでした。
それにしても、中国の神仙、天竺までの仏僧行脚、日本の八百万神、江戸初期の切支丹ときて、ついにギリシアの神々と、宗教観を取り入れることで小説としての深みが増していきます。世の中には単に設定として使う作品も多いですが、しっかり考証されているので知的好奇心をも刺激してくれるのが素晴らしいです。
さて、中国でも日本でもなく、古代(神代)とはいえ西欧での物語、しかして中身は現代日本の若者たちの青春群像なのですが、ギリシア神話の名だたる神や英雄たちが続々と登場して活躍する展開が新鮮で楽しいものでした。
もちろん、その筆頭は魔神・テューポーンで、そのかわいらしさにすっかり魅せられてしまいます(本来は荒ぶる男神のはずなのですが、神に性別はないと本人も言っております)。アニメなどでよくある萌えキャラタイプであると言えばそうで、当然に作者もそこを狙ってキャラを立てていると思われますが、しかしそれだけでは終わらない、神としての奥深さが描かれているところが魅力です。
それは、神の時間と人の時間の違いなのかもしれません。神と人が融合するというこの話の肝は、そこにあるかと思います。古代と現代の時の壁を超える経験をした神や人たちが、そのうち出るだろう2巻ではもっとダイナミックに動き回るかと思うと、続きが楽しみです。
それにしても、ギリシア神話は小学生の頃に児童書で読んだ記憶があるくらいですが、とんでもない神様たちの話です。こんな話が何千年も前に生まれていたというのが驚きです。中国4千年の歴史もすごいですが、そこにキリストやブッダや孔子が生まれた文化的ベースがあるわけです。
それに比べて日本の神話なんてちっぽけなものだよなぁと思ったり。別に小さいことは悪くないのですが。日本が神国だなんて勘違いするたびに大きな過ちを冒してきたわけで、日本文化の素晴らしい神髄はもっと別のところにあるのだと理解していなければなりません。と、いつも仁木氏の作品には気付かされるのです。
テューポーン以外にも、幼なじみの女の子や双子の女の子、介抱してくれたギリシアの少女もまた登場してほしいしと、なかなかステキな女性も多く、どんな展開を描いてくれるか。もちろん、男どもの熱いバトルアクションや冒険も見所ですが。主人公の性格がちょっと・・というところも、変に感情移入し過ぎないので良いのかも知れません。続巻を待望することにしましょう。
「ビブリア古書堂の事件手帖2 〜栞子さんと謎めく日常〜」三上延(メディアワークス文庫)を読了。
 1巻目を古本屋で買って読んで間もないですが、今回は新刊で買っての読書です。引き続き私の地元である大船を中心に、鎌倉や藤沢方面にも広がりを見せる舞台。私の家の前も、主人公二人が車で通っていきました……。
1巻目を古本屋で買って読んで間もないですが、今回は新刊で買っての読書です。引き続き私の地元である大船を中心に、鎌倉や藤沢方面にも広がりを見せる舞台。私の家の前も、主人公二人が車で通っていきました……。
と、生まれ育った町の隣接エリアで、今は住んでいる辺りが舞台ですので、近々、聖地巡礼ブログでも書こうかと考えているのですが、その前にこの街について、ちょっとだけ紹介しておきましょう。
大船駅からして鎌倉市と横浜市の両方にまたがる場所にあるのですが、神奈川県内で横浜駅に次ぐ鉄道路線が乗り入れるビッグターミナルなのです。大船エリアとして広げれば、少し行くと藤沢市と接するあたりで、鎌倉市民でも大船は鎌倉市ではないと(差別的に)言う者がいたり、余所の人からは大船市であると誤解されていたりもしますが、3市のどことも違う、独特の雰囲気や街の文化があります。
そのあたりは本作でもかなり描かれていますが、かつて松竹の撮影所があり、屈指の私立学校があり、古城跡や古刹があり、植物園がありコンサートホールがあり、商店街が賑わい多くの飲食店がある、というような、なんともとりとめのないところが逆に奥深さを作っている、そんな街で‥‥やはり、あらためて紹介することにしましょう。
ちなみに、本巻に登場していた駅前の本屋さんは、昨年閉店してしまいました。街は常に変わり続けるというのも、またノスタルジアを感じさせてくれるものです。
さて、話を本に戻して、2巻目は1巻目よりもラノベ感が強くなった気がします。ヒロイン栞子の萌え要素や、主人公大輔の恋情妄想など、気恥ずかしいくらいですが、しかしながら、古本の蘊蓄をうまくストーリーに取り込みつつ、1冊の中でうまく全体の物語を構成していく手腕は、本格的な小説の面白さを味わわせてくれて見事です。
登場する古書も、随筆、SF小説、ビジネス書、マンガとバラエティ豊か。一つの方向に片寄らないところが、読者を選ぶことなく誰もが楽しめる作品になっているかと思います。それがまた、栞子の不思議なキャラクター付けにもつながるわけですが。
2巻目にして、栞子さんと大輔くんの過去にも少しずつ踏み入り、明らかになってきました。今後、栞子さんのミステリアスなお母さんが物語の核になってきそうで、ますます期待してしまいます。
栞子さんは、退院して家(店)に帰ってきて、いろいろとダメっぷりを見せています。無意識に大輔くんを頼ってくる、そこがかわいいけれど、人としてはもう少しなんとかできないといけません。どんな成長を見せてくれるか、今後の進展も楽しみです。
それに対して大輔くんは、なかなか男を見せてくれます。ちょっと軟弱に書かれすぎていましたが、本来がガタイの良い柔道マンなのですから、もっと活躍してしかるべきかと。
その他、元カノ晶穂さんをはじめとする個性的な人たち、そして1巻で登場した主要人物もところどころに絡んでくるので、作品への愛着が強くなってきます。
ようやく物語も軌道に乗り始めたところ、人物のキャラクター性も徐々に深まってきて、まだまだ続くようですので、先々がとても楽しみな作品となってきました。
と、生まれ育った町の隣接エリアで、今は住んでいる辺りが舞台ですので、近々、聖地巡礼ブログでも書こうかと考えているのですが、その前にこの街について、ちょっとだけ紹介しておきましょう。
大船駅からして鎌倉市と横浜市の両方にまたがる場所にあるのですが、神奈川県内で横浜駅に次ぐ鉄道路線が乗り入れるビッグターミナルなのです。大船エリアとして広げれば、少し行くと藤沢市と接するあたりで、鎌倉市民でも大船は鎌倉市ではないと(差別的に)言う者がいたり、余所の人からは大船市であると誤解されていたりもしますが、3市のどことも違う、独特の雰囲気や街の文化があります。
そのあたりは本作でもかなり描かれていますが、かつて松竹の撮影所があり、屈指の私立学校があり、古城跡や古刹があり、植物園がありコンサートホールがあり、商店街が賑わい多くの飲食店がある、というような、なんともとりとめのないところが逆に奥深さを作っている、そんな街で‥‥やはり、あらためて紹介することにしましょう。
ちなみに、本巻に登場していた駅前の本屋さんは、昨年閉店してしまいました。街は常に変わり続けるというのも、またノスタルジアを感じさせてくれるものです。
さて、話を本に戻して、2巻目は1巻目よりもラノベ感が強くなった気がします。ヒロイン栞子の萌え要素や、主人公大輔の恋情妄想など、気恥ずかしいくらいですが、しかしながら、古本の蘊蓄をうまくストーリーに取り込みつつ、1冊の中でうまく全体の物語を構成していく手腕は、本格的な小説の面白さを味わわせてくれて見事です。
登場する古書も、随筆、SF小説、ビジネス書、マンガとバラエティ豊か。一つの方向に片寄らないところが、読者を選ぶことなく誰もが楽しめる作品になっているかと思います。それがまた、栞子の不思議なキャラクター付けにもつながるわけですが。
2巻目にして、栞子さんと大輔くんの過去にも少しずつ踏み入り、明らかになってきました。今後、栞子さんのミステリアスなお母さんが物語の核になってきそうで、ますます期待してしまいます。
栞子さんは、退院して家(店)に帰ってきて、いろいろとダメっぷりを見せています。無意識に大輔くんを頼ってくる、そこがかわいいけれど、人としてはもう少しなんとかできないといけません。どんな成長を見せてくれるか、今後の進展も楽しみです。
それに対して大輔くんは、なかなか男を見せてくれます。ちょっと軟弱に書かれすぎていましたが、本来がガタイの良い柔道マンなのですから、もっと活躍してしかるべきかと。
その他、元カノ晶穂さんをはじめとする個性的な人たち、そして1巻で登場した主要人物もところどころに絡んでくるので、作品への愛着が強くなってきます。
ようやく物語も軌道に乗り始めたところ、人物のキャラクター性も徐々に深まってきて、まだまだ続くようですので、先々がとても楽しみな作品となってきました。
2012年3月16日・金曜日、いつものように残業しての帰途。座って帰るために東京駅始発電車に乗るので、いつも新橋駅から東京駅まで東海道線を利用します(ちゃんと東京駅までの定期券を買ってるので、無賃乗車ではありませんよ)。
普通は15両編成ですが、22時39分の電車は9両編成・2つドアの、特急にも使われる車両がやって来ます。この日も、ああこれかぁと、なんかいつもよりは混んでるなぁと、そんな感じでした。
東京駅に着くときの車内アナウンスで、「間もなく終点の東京駅です、どなたさまもお忘れもののないよう〜」というような普通どおりの言葉の後に、「なお、本列車は本日、この運行をもって最後となります。長い間ご利用ありがとうございました…」みたいな付け足しがさらりと。私はまったく知らなかったのですが、この373系電車は、翌日からダイヤ改正となるので、これがラストランだったのです。
滑り込んだ東京駅のホームには、カメラを構えた鉄道ファンの皆さんが群がっていました。乗っている人の中にも、結構いたのではないかと思います。
 降りたその場で私も写真を撮っておこうかと思いつつ、時間もないのでそのまま隣のホームに移動してしまったのですが、せめてもと、そちらから1枚。なんだかよくわかりませんが、心の思い出ということで。
降りたその場で私も写真を撮っておこうかと思いつつ、時間もないのでそのまま隣のホームに移動してしまったのですが、せめてもと、そちらから1枚。なんだかよくわかりませんが、心の思い出ということで。
ついに特急として運行される便に乗ったことはありませんでしたが、この時間の帰宅時と、徹夜残業をして始発で帰るときには、この車両が普通列車として使われていたので、たまに利用していました。外見は特急らしくないデザインながら、中の座席はなかなかに快適で、好きな電車でした。
なんか、最初に登場した当時から地ってるだけに、もう引退なの?という感じですが、自分が歳をとったということでしょうね。
たまたま最後の運行に乗り合わせることが出来た、鉄道は好きだけれどマニアではない私ですが、寂しくも嬉しいことでした。
普通は15両編成ですが、22時39分の電車は9両編成・2つドアの、特急にも使われる車両がやって来ます。この日も、ああこれかぁと、なんかいつもよりは混んでるなぁと、そんな感じでした。
東京駅に着くときの車内アナウンスで、「間もなく終点の東京駅です、どなたさまもお忘れもののないよう〜」というような普通どおりの言葉の後に、「なお、本列車は本日、この運行をもって最後となります。長い間ご利用ありがとうございました…」みたいな付け足しがさらりと。私はまったく知らなかったのですが、この373系電車は、翌日からダイヤ改正となるので、これがラストランだったのです。
滑り込んだ東京駅のホームには、カメラを構えた鉄道ファンの皆さんが群がっていました。乗っている人の中にも、結構いたのではないかと思います。
ついに特急として運行される便に乗ったことはありませんでしたが、この時間の帰宅時と、徹夜残業をして始発で帰るときには、この車両が普通列車として使われていたので、たまに利用していました。外見は特急らしくないデザインながら、中の座席はなかなかに快適で、好きな電車でした。
なんか、最初に登場した当時から地ってるだけに、もう引退なの?という感じですが、自分が歳をとったということでしょうね。
たまたま最後の運行に乗り合わせることが出来た、鉄道は好きだけれどマニアではない私ですが、寂しくも嬉しいことでした。
「くるすの残光 天草忍法伝」
「くるすの残光 月の聖槍」
仁木英之著(祥伝社刊)
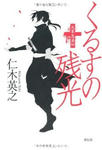
「月の聖槍」が出て買おうとしたところ、前の巻があったことにはじめて気付いて、あわてて注文しました。仁木作品は8割方読んでいるのではないかと思うのですが、作者の精力的な執筆ペースに着いて行けてない感じです。
そんな多作の作者、これまでの作品で描いてきた要素がうまく結実している気がします。千里伝のヒーローキャラや、僕僕のロードストーリーや、黄泉坂の妖や、海遊記の坊さんや・・・一作ごとに、歴史・民俗・人間などへの思考が積層し、思想を形成していく、そんな過程が見えるようで、まだまだ先が楽しみな小説家さんです。
2の帯に「風太郎忍風帖への最高のオマージュ〜」というコピーがありましたが、山田風太郎を読んだことのない私にとって、本作は白土三平を想起させながらの読書となりました。作者の「飯縄颪(いずなおろし)」という忍者作品がありましたが、あれはタイトルからも明らかに「カムイ伝」を意識していたと思われるので、白土比較も間違ってはいないかと思います。
権力に抑圧された人間を描き、また力に魅入られた人間を描く、その中で生と死を見つめる・・・そうした作風は「カムイ伝」の1部よりは2部、そして武芸に重きを置いた外伝に近い世界だと感じました。
とは言いながら、仁木作品はしっかりと歴史物の体裁を保ちながらも、いまのアニメ的な演出や萌え要素も含んでいるのが、この時代に受け入れられている理由と思っています。本作でもビジュアルが思い浮かぶ魅力的なキャラクター作りが巧いなと、感服しました。
天草の乱についてはあまり詳しくありませんでしたが、なぜ時の権力者が切支丹を根絶しようとしたか、そうした理由が納得できるように書かれています。その中で、天草四郎の意志と力を受け継いだ主役である者たちが苦悩しながら闘う姿は、盲信的な信仰を越えて、生きることの意味に迫ります。
それは決して過ぎ去った時代のことだけではなく、現代においても平和で自由な時代に見えて、同じような権力者による思想統制や踏み絵のようなことがことが行われているわけです。表向き泰平の世であっても、庶民は生きることに必死である、そうした私達に近い存在だと思いました。
と、感想を書こうとすればいろいろな思考が廻ってしまうのですが、読んでいる時は忍者モノの活劇として楽しめます。そしてまだまだこの先も数巻は続いて行くと思われるので、その物語の中で派手な闘いも、純な恋情も、辛い葛藤や強い決意もあるでしょう、クライマックスには天草四郎が復活するのか・・・など、大いに期待を膨らませながら、次を待ちたいと思います。
「くるすの残光 月の聖槍」
仁木英之著(祥伝社刊)
「月の聖槍」が出て買おうとしたところ、前の巻があったことにはじめて気付いて、あわてて注文しました。仁木作品は8割方読んでいるのではないかと思うのですが、作者の精力的な執筆ペースに着いて行けてない感じです。
そんな多作の作者、これまでの作品で描いてきた要素がうまく結実している気がします。千里伝のヒーローキャラや、僕僕のロードストーリーや、黄泉坂の妖や、海遊記の坊さんや・・・一作ごとに、歴史・民俗・人間などへの思考が積層し、思想を形成していく、そんな過程が見えるようで、まだまだ先が楽しみな小説家さんです。
2の帯に「風太郎忍風帖への最高のオマージュ〜」というコピーがありましたが、山田風太郎を読んだことのない私にとって、本作は白土三平を想起させながらの読書となりました。作者の「飯縄颪(いずなおろし)」という忍者作品がありましたが、あれはタイトルからも明らかに「カムイ伝」を意識していたと思われるので、白土比較も間違ってはいないかと思います。
権力に抑圧された人間を描き、また力に魅入られた人間を描く、その中で生と死を見つめる・・・そうした作風は「カムイ伝」の1部よりは2部、そして武芸に重きを置いた外伝に近い世界だと感じました。
とは言いながら、仁木作品はしっかりと歴史物の体裁を保ちながらも、いまのアニメ的な演出や萌え要素も含んでいるのが、この時代に受け入れられている理由と思っています。本作でもビジュアルが思い浮かぶ魅力的なキャラクター作りが巧いなと、感服しました。
天草の乱についてはあまり詳しくありませんでしたが、なぜ時の権力者が切支丹を根絶しようとしたか、そうした理由が納得できるように書かれています。その中で、天草四郎の意志と力を受け継いだ主役である者たちが苦悩しながら闘う姿は、盲信的な信仰を越えて、生きることの意味に迫ります。
それは決して過ぎ去った時代のことだけではなく、現代においても平和で自由な時代に見えて、同じような権力者による思想統制や踏み絵のようなことがことが行われているわけです。表向き泰平の世であっても、庶民は生きることに必死である、そうした私達に近い存在だと思いました。
と、感想を書こうとすればいろいろな思考が廻ってしまうのですが、読んでいる時は忍者モノの活劇として楽しめます。そしてまだまだこの先も数巻は続いて行くと思われるので、その物語の中で派手な闘いも、純な恋情も、辛い葛藤や強い決意もあるでしょう、クライマックスには天草四郎が復活するのか・・・など、大いに期待を膨らませながら、次を待ちたいと思います。
カレンダー
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
フリーエリア
最新CM
[06/01 WaxJelia]
[01/25 本が好き!運営担当]
[03/27 うらたじゅん]
[10/28 のりこ]
[08/04 つばめろま〜な]
最新記事
(01/21)
(12/30)
(01/02)
(02/06)
(01/01)
最新TB
プロフィール
HN:
つばめろま〜な
性別:
男性
趣味:
絵・音・文・歩
自己紹介:
長年、同人誌で創作漫画を発表してきましたが、本当は小説が主な表現手段。職業はコピーライターで、趣味は楽器を鳴らすことなど。
下記に作品等アップ中です。よろしくお願いします!
■マンガ作品 COMEE
http://www.comee.jp/userinfo.php?userid=1142
■イラスト作品 pixiv
https://www.pixiv.net/users/31011494
■音楽作品 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UChawsZUdPAQh-g4WeYvkhcA
■近況感想雑記 Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005202256040
下記に作品等アップ中です。よろしくお願いします!
■マンガ作品 COMEE
http://www.comee.jp/userinfo.php?userid=1142
■イラスト作品 pixiv
https://www.pixiv.net/users/31011494
■音楽作品 YouTube
https://www.youtube.com/channel/UChawsZUdPAQh-g4WeYvkhcA
■近況感想雑記 Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005202256040
ブログ内検索
最古記事
(09/30)
(10/06)
(10/10)
(10/12)
(10/12)
P R
忍者アナライズ
忍者アナライズ
忍者アナライズ
忍者アナライズ

